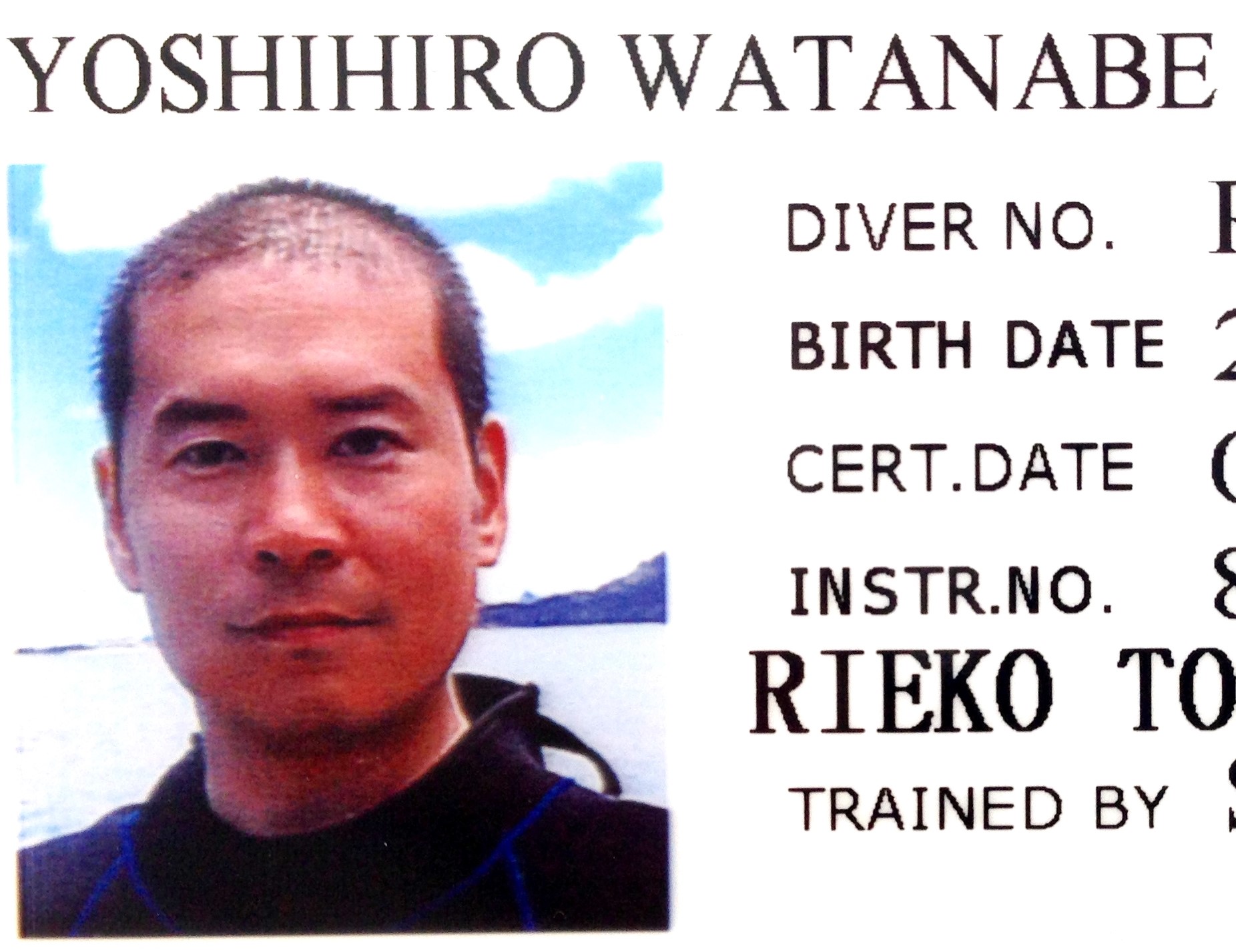『てくてく常滑』(1歩目~大野町周辺~)を常滑市立図書館に寄贈する。
これは、街歩きの記録を地域資料として図書館に寄贈して閲覧を可能にするプロジェクト、「てくてく友の会」の成果物。
「てくてく友の会」は地域資料(コンテンツ)の創造とアーカイヴ化を通じて、新旧住民の間、図書館と地域の間、
オンラインとオフラインの間をつなぐ、「情報のかけ橋」として位置づけている。
この位置づけの下で、これまで文京区(5冊)と松阪市(6冊)で地域資料を作り、そのモデルの提案として市民講座や国際ワークショップで発表してきた。
今回の『てくてく常滑』は、常滑市に来たばかり(3ヶ月)の人と常滑市に生まれ育った人が参加して、新旧住民のかけ橋という意味合いがより一層強いものとなった。
常滑市は人口流動性が高まり(10年で10%の人口増加)、これまでの住民とこれからの住民とが対話するメディアの創造を課題としている。
今回はその地域課題に対する一つの提案という意味合いも含めての取り組みとなった。
表現(情報発信・コンテンツ創造)を通して、人と人、地域と人の間に「情報のかけ橋」をかけることは自分のテーマでもある。
「てくてく」の文字通り、一歩を踏み出すこと、一歩ずつ続けていくことの大切さを表現しながら、「情報のかけ橋」の構築に貢献していきたい。
※1:参考リンク:
・『てくてく文京』が文京区立図書館で閲覧可能になる
・松阪市民講座;「地域の魅力を発見発信講座-街歩き『てくてく松阪』を通した地域資料作りのすすめ-」の講師をつとめる
・松阪市民講座;「平成23年度 地域の魅力を発見発信講座-街歩き『てくてく松阪』を通した地域資料作りのすすめ-」の講師をつとめる
・I presented “A Workshop ‘TEKUTEKU’: Creation and Preservation of Local Information Linking Outdoor Activities to Public Libraries” at IWRIS2012.
・『てくてく松阪』が合併前の全市町を網羅する
※2:報道歴:
2011年4月25日 『夕刊三重』・第1面「てくてく友の会 歩いてわが町を紹介 松阪市特別職渡邊さんら 冊子に編集し図書館で活用」
2011年4月29日 『中日新聞』朝刊・第20面「松阪の魅力 歩いて発見 住民有志が情報誌作成 史跡や飲食店を満載」
2011年9月27日 『夕刊三重』・第1面「三重中京大学生ら デートスポット 地図に 未来の閉学控え軌跡残したい 松阪港やプラネタリウム」
2012年10月27日 『中日新聞』朝刊・第20面 「図書館で紡ぐ地域づくり てくてく活動を学会発表 松阪の渡辺さん ネットの仲間で街歩き集めた情報冊子で開示」
2012年11月14日 『中日新聞』夕刊・第3面 「人と街 てくてく結ぶ 三重・松阪 ネットで交流 集めた情報 冊子に」
2014年6月26日 『中日新聞』朝刊・第22面 「足で収集 まちの情報発信 常滑の3人、冊子を発行」
2014 6/21
出来事メモ