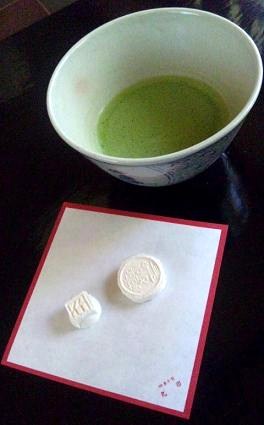堺にある銀シャリ屋ゲコ亭で白御飯をいただく。
この銀シャリ屋ゲコ亭は大衆食堂だけど、とにかくご飯にこだわっていることで知られている。
まず、ご飯を炊くことに集中するために、ご主人はおかずを一切つくらない。
コシヒカリとササニシキを独自にブレンドしたお米を、その日の天候を判断しながら井戸水と自家製釜で炊き上げるその腕は名人芸とまで呼ばれている。
しかも、お米が古くなるのと水が美味しくなくなるという理由から夏の三ヶ月は休業するという徹底ぶり。
・・・なのだけど、賛否両論の声をよく耳にする。
(中にはご主人のご飯よりも奥さんの卵焼きの方が美味しいという声まで)
本当に美味しいのかどうかを確認するために、今回はフフレとおとずれて実食。
食べてみると、お米の甘味が感じられるやわらかなご飯で個人的には美味しく感じられた。
ただし、かなりやわらかい炊き上がりというところが好みの分かれるところなのも理解できた。
ご飯の炊き方には好みが分かれるものだけど、かための方が好きな人にとっては違和感があるものらしい。
好みは分かれるけれど、それはお米の国である日本人である証拠。
ご飯についてこだわった名店ではあることは確かであることは感じられた。
ご飯の美味しさについて議論する機会も提供してくれるお店でもある。
まろまろと今日ももぐもぐ。
大阪・堺の「銀シャリ屋 ゲコ亭」にて。